化学系博士たちが語る“ものづくり”への情熱とリアル ~旭化成×パナソニック インダストリー~
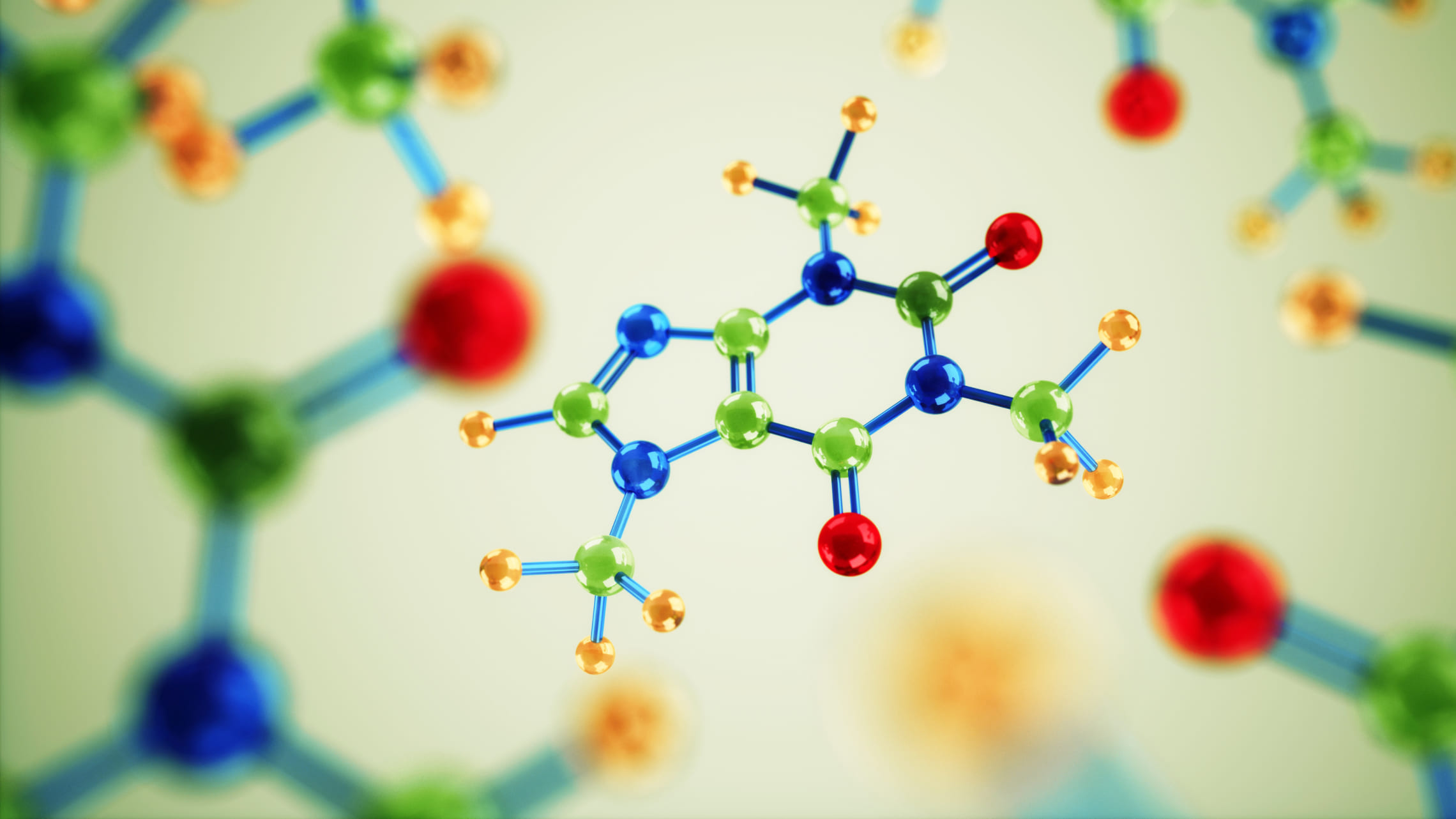
この記事のポイント
- アカデミアと産業界は対立ではなく螺旋:「探求に終わりはなく、最初の場所に戻る」—両者を往復しながら新しい価値観を獲得する研究者像
- 「巻き込む力」がイノベーションを生む:自分の好きなことを社会課題と紐付け、多様な専門家(マーケティング、製造現場など)を巻き込むことで前進する
- 「今しかできない研究」への情熱:社会が今必要とするテーマに、最先端技術をフル活用して挑むスピード感とダイナミズム

赤尾津 翔大(工学博士)
旭化成株式会社 人事部 新卒採用担当
大学では石炭の化学反応をコンピュータシミュレーションで予測する研究に取り組み、博士号(工学)を取得。卒業後は旭化成に入社し、フッ素系樹脂の新規製造プロセスの研究開発職として、材料の設計から合成、評価まで一貫して取り組む。専門の幅を広げるため、ゲノム解析のベンチャーでシステム開発の副業にも従事。その後、人事部に異動し、現在は化学系とバイオ系の新卒採用担当として奮闘中。

齊藤 輝彦(理学博士)
パナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部 技術開発センター 基盤技術開発部
2009年大阪大学基礎工学部を卒業後、同大学院に進学。有機金属化学の研究に取り組み2014年に博士(理学)を取得。同年、京都大学大学院工学研究科で博士研究員を経験し、その後、大阪大学大学院基礎工学研究科の助教に着任。2016年10月パナソニック株式会社に研究の場を移し、マサチューセッツ工科大学との2年間の共同研究も経験。共同研究で得た樹脂技術の知見を活かし、2022年からパナソニック インダストリー株式会社 電子材料事業部で次世代半導体パッケージ用の材料開発を行っている。専門は、有機金属化学、高分子化学。
summary
先日開催されたLabBase WORLDの対談イベント「化学系博士たちが語る"ものづくり"への情熱とリアル」は、学生が気になるトピックを本音で語ったり、視聴学生からの質問にその場で回答したりと、大盛り上がりとなりました。今回はそのライブ感をダイジェストとしてお届けします。
①大学の研究と企業の研究、何が違う?
赤尾津:まず『関わる人の多さ』と『スケール感』ですね。大学は自分の領域を極める感じだけど、企業はラボスケールじゃ終わらない。実際にモノを作る製造現場の人たちと『ああでもない、こうでもない』って議論しながら、世の中に供給できる体制を作る。目的も『社会やお客様』になるので、『自分が世界を変えるんだ!』っていう責任とやりがいがあります。
齊藤:僕は『問いの解像度』が違うと感じます。企業にはマーケティングや広報など、アカデミアでは関わらない職種の人がたくさんいる。そういうお客様に一番近い人たちから、すごくリアルで良い「問い」をもらえるんです。
②「好きな研究」と「会社のミッション」、両立できる?
齊藤:『やりたい!』っていう内発的な興味と、『社会やお客様の課題』、この両方のバランスがめちゃくちゃ大事。そこで必要なのが『巻き込む力』です。自分の好きなことが『本当に社会のためになるんだ!』ってビジョンと繋がっていれば、人はどんどん協力してくれる。もし巻き込めなかったら、独りよがりになってないか考え直すチャンスですね。
赤尾津:僕も専門外の実験チームに入った時、最初は戸惑いました。でも、自分の専門であるシミュレーションを『会社の目標達成にこう使えるはず!』って、自分のベクトルの向きを会社の目標に合わせることで、両立できると感じましたね。
③博士キャリアは「螺旋階段」だ!
齊藤:アカデミアと企業は対立じゃなくて、螺旋階段みたいに往復しながら上に進んでいくイメージです。『探求に終わりはなく、最初の場所に戻る』っていう好きな言葉があります。僕もアカデミアから企業に行って、またアカデミアで学んで、企業に戻ってきた。いろんな経験を通して新しい価値観を広げていけるんです。
赤尾津:僕のキャリアも『偶然の要素』が本当に多かった。まさか自分が人事をやるなんて1ミリも想像してなかった(笑)。でも、そういう出会いや偶然で人生が変わるのも面白い。だから、あまり固く考えすぎなくていいんじゃないかな。
④企業ごとの違いは?
赤尾津:旭化成は「若手の裁量権」が特徴です。「自分が解決する」という姿勢が求められ、若手とベテランが分け隔てなく議論する文化があります。私も入社半年でプラント入れ替えを担当し、責任を感じつつも成長に繋がりましたね。もちろん、上司が頻繁にコミュニケーションを取り、手厚くフォローしてくれる環境もあります。
齊藤:インダは多様な事業があり、それぞれと社会の繋がりが明確な点ですね。大企業では個人は歯車と思うかもしれないですが、インダではその歯車が社会のどこに繋がっているのか、貢献できるのかがわかりやすい。「事業は人なり」として個人の裁量も大切にしつつ、チームで成果を出すことを重視し、研修による人間教育も定期的に行っている点も特徴です。
⑤お二人の「情熱」の源泉は?
齊藤:企業に来て感じるのは、今しかできない研究があるということです。アカデミアでは長期的な視点で研究できますが、企業では社会の動きやお客様のニーズに合わせて、今この瞬間にやるべきことがある。そのスピード感とダイナミズムは企業ならではだと思います。
具体的には、私は今、半導体パッケージ用の材料開発をやっています。みなさんのスマホやAIを支える、本当に世の中に必要とされている材料です。自分たちの研究開発が世の中のためになるんだということがはっきりしている。社会へのインパクトも大きい。そういうやりがいのある領域を見つけられています。
赤尾津:自分の研究が実際に製品になって世の中に出ていくというのは、何物にも代えがたい喜びですね。私は特に「時間」を意識しています。実験だけでなく、シミュレーションや機械学習といった最先端の技術をフル活用して、いかに早く作りたいものを作り上げるか。企業で研究できる時間は限られていますから、自分の軸を活かして早くつくることを大切にしています。
⑥化学系学生へ「今しかできないことに熱中してみよう!」
齊藤:今いる研究室での時間はとても貴重なので、ぜひ大切にしてください。研究成果も大事ですが、研究のプロセスも大事です。研究室での先生や先輩後輩、同級生との関係を大切にしてください。一つの小さな会社みたいなもので、そこで人間関係やチームワークを学ぶことが、社会に出てからも活きてきます。
赤尾津:まさに!『今の研究生活に熱中してください』。自分の興味があることに、とことん打ち込んだ経験は、将来絶対にあなたの強みになります。ぜひ今の環境でそれを磨いてください!もちろん研究以外の課外活動でも、熱中できることが見つかっているなら、それを一生懸命やってみましょう。
まとめ
研究を頑張る学生のキャリアは一本道とは限りません。お二人のように、専門性を軸にしながらも、偶然を楽しみ、周りを巻き込んで新しい価値を生み出していく....。そんなワクワクする未来が待っているかもしれません。
就職活動というと、「いかに内定を勝ち取るか」という感覚になることがあるかもしれません。しかし、「自分が社会に対してどのような影響を与えられるのか」「自分の力を世の中でどう発揮できるのか」という自分の可能性を模索する試みとも考えられます。悩んだり迷ったりする瞬間もたくさんあると思いますが、視点を変えると実は前向きに楽しめる活動なのではないでしょうか。
2社のリアルを自分の目で確かめにいきませんか?
登壇企業へのエントリーはこちら!
本編で回答出来なかった質問に全回答している「延長戦」を閲覧したい方はこちら
